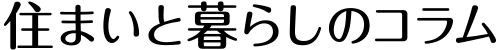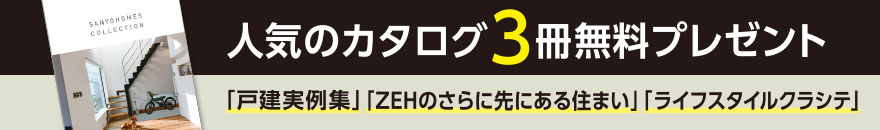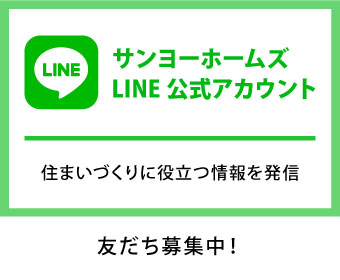家の購入に関して、戸建てかマンションかを悩む人も多いと思います。その結果、注文住宅を購入することに決めた場合、住宅の建築にあたって、耐火構造の基準を守らなければならないケースもあります。
今回は耐火構造の基準について解説するとともに、なぜ耐火構造を取り入れることが大切なのかについても紹介します。これから注文住宅を建てようと思っており、耐火構造の基準や仕組みについて気になっている人はぜひ参考にしてください。
耐火構造の基準について
耐火構造とは建築基準法にて定められているもので、火災が終わるまでに家屋の崩壊などを防止するための必要な機能を指し、遮熱性はもちろん遮炎性、非損傷性を備えていなければなりません。
また、建物の構造部位によって求められる性能が異なっている点も特徴です。耐火構造は木造住宅密集地域における、震災時の延焼を防止するといった重要な目的を備えています。
日本でも2020年3月に改定された防災都市づくり推進計画において、さまざまな整備事業を実施するとともに、土地の利用施策によって延焼遮断帯の形成、および建物の不燃化や耐震化を促進しています。
木造住宅密集地域とは、震災があった際に、延焼被害の恐れが高いとされている、古い木造住宅が密集している地域を指します。具体的な場所は東京都の出火防止対策促進事業のサイトで確認できます。
耐火構造の基準については性能の高い順に、以下の3つに分類されます。
・耐火構造
・準耐火構造
・防火構造
それぞれの違いについて、以下で詳しく説明します。
耐火構造とは?
耐火構造とは、家屋の壁もしくは床などが一定の耐火性能を備えていることを指します。ここで言う耐火性能とは、火災が発生した際、鎮火するまでに建物が崩壊しないことや、火災発生時に隣家に延焼しない性能で、基準に応じた一定時間の火災に耐えられなければなりません。
火災に耐えられる時間は構造の種類や建物の階数によって異なり、例えば、建物の階数(最上階から数えた階数)が15階以上の場合、壁や床が2時間、柱や梁は3時間、屋根や階段は30分となっています。
また、耐火構造の基準を満たすには建物の主要構造の仕様が国土交通大臣の認定を受けたものでなければならず、具体的には鉄骨鉄筋コンクリート造や鉄骨造などが当てはまります。
そして、耐火構造の仕様を満たす構造で建てられ、さらに防災区画や防災設備などが設置された建築物が耐火建築物です。
準耐火構造との違いは?
準耐火構造とは、耐火構造よりも基準が緩やかになっており、通常の火災による延焼を防ぐために必要な構造がなされているものを指します。
準耐火構造が当てはまる建物は、最長1時間の火災に耐えられるものでなければならず、建物の主要構造によって火災に耐えられる基準時間が決まっています。
具体的には、間仕切り壁や外壁、床、柱、階段は45分とされており、屋根については、延焼の恐れのある部分については45分、それ以外の部分や軒裏以外は30分です。
また、奥内側からの火災については、外壁は、非耐力壁の場合は30分でなければならず、屋根についても30分とされています。
建物の構造としては瓦をはじめ、金属板やモルタル、石膏ボードといった不燃材料を使わなければなりません。
耐火構造と同様に、準耐火構造で建てられ、さらに防災区画や防災設備などが設置された建築物を準耐火建築物といいます。
防火構造って?
施設やマンションなど多くの人が暮らす建物の場合、耐火構造もしくは準耐火構造で建てなければなりません。また、家を建てようとしている地域が防火地域、もしくは準防火地域の場合も同様です。
ただし、小規模な住宅なら、耐火構造や準耐火構造ではなく防火構造で建てることが可能です。
防火構造とは、周りの建物から発生した通常の火災の際に、延焼を抑えるために必要な性能を備えるものです。延焼に巻き込まれないように外壁や軒裏の部分に防火性能を備えた材料を使用することで、30分間熱にさらされても変形や破壊などが起こらず、材料の表側の熱が出火温度に達成しない工夫がなされています。
具体的には、外壁の外側を鉄鋼モルタルで塗装し、そして内側には石膏ボードを張るなどです。
防火構造では、外側は防火性能のある材質を利用しなければなりませんが、柱などは自由に選べるため、建築費用が抑えられるといったメリットが得られます。反面、防火構造はあくまでも外からの延焼を防ぐことを目的としているため、内側に炎が入った場合には建物が崩壊する可能性が高い点に注意が必要です。
耐火構造が火災の危険から家族を守る3つの理由
・隣家からの「もらい火」の影響を軽減する
・隣室や隣家への延焼を抑える
・防火玄関ドアなら火の侵入を遅らせる
隣家からの「もらい火」の影響を軽減する
上でも述べたとおり、耐火構造は火災が起こった際に安全に避難できるほか、消火活動を行える時間を備えています。耐火時間を最大3時間に定めているのもそのためです。
また、建物の主要構造も耐火基準を満たしているため、もし隣家から火災が発生したとしても耐火性能が高いため、燃え移る可能性が低くなります。
耐火構造は火災による家屋の崩壊そして延焼を防ぐ構造になっています。仮に隣家から出火した場合、外壁は約800度以上の温度にさらされますが、耐熱素材を使用して建設することでもらい火の影響を軽減できるのです。
隣室や隣家への延焼を抑える
耐熱素材で建てた耐火構造の家屋は、火災が発生した際の隣室や隣家への延焼を抑えることが期待できます。
火災の被害は隣家からの延焼だけでなく、自宅からの発火が原因になるケースも考えられます。しかし、耐火素材を使うことで、建物内での発火自体を防ぐことができるほか、もし発火したとしても建物の中で火災が広がることなく、また隣家の延焼を抑えられます。
耐火構造で使用される素材は厚みがあるものが多く、基本的に厚みの大きさが耐火時間に比例します。
建物の部位によって利用する素材は異なりますが、できるだけ鉄筋コンクリート造のものを利用するとよいでしょう。
防火玄関ドアなら火の侵入を遅らせる
玄関ドアを耐火構造にすることで、ドアからの火の侵入を遅らせることが期待できます。
サンヨーホームズで扱っている防火玄関ドアは、一定の温度に達するとドアの小口に張られている加熱発泡材が発泡し、5~40倍に膨張して隙間を塞ぎ、炎の侵入やもれを防げます。
サンヨーホームズでは、防火玄関ドア以外にも耐火性に優れた十分な厚みのあるALC床パネルを採用するほか、壁についてもALC素材を利用した耐火性のある家作りに貢献しています。
まとめ
木造住宅密集地域など、古い木造住宅が多い地域では、災害が起きた際に被害が拡大しないよう、国を挙げて対策を講じています。火災による災害を広げないためには、火をもらわない工夫や火を広がらせない配慮のほか、火災の延焼を抑える耐火構造が必須です。
サンヨーホームズでは、1時間の耐火基準を誇るUrbanを取り入れており、耐火構造の相談にもお応えできます。また、理想の住まいは暮らし方によって変わっていきます。建てた後のリフォームや住み替え、建て替えといった悩みを解決するだけでなく、より快適に過ごすための提案もさせていただきます。
耐火構造の注文住宅建築について悩んだ際には、ぜひサンヨーホームズにご相談ください。
カテゴリー:
新着記事

基礎知識
狭小住宅のメリット・デメリットは?土地に制限があ…
狭小住宅とは、住宅の中でも住宅が建てられている土地が狭いものを指します。狭小住宅

基礎知識
賃貸併用住宅とは?気になるメリット・デメリットと…
住宅には自分達だけが住む仕様以外に、あわせて賃貸収入が得られるよう、賃貸スペース

基礎知識
福岡県で注文住宅を建てたい!気になる費用相場や建…
これから福岡県に注文住宅を建てるなら、費用相場はどのくらいなのか、また人気のエリ

基礎知識
愛知県名古屋市で注文住宅を建てるときの費用相場は…
これから愛知県名古屋市で注文住宅を建てたい人にとって、建築費用相場や人気の居住エ

基礎知識
インナーガレージの間取りを考えるコツ!後悔しない…
注文住宅の購入を考えている方に向けて、インナーガレージのある家の間取りのアイデア

基礎知識
賃貸併用住宅で住宅ローンを組むなら?土地活用に役…
建て替えや住宅の建設目的での土地活用を考えており、せっかくなら賃貸併用住宅を建て
おすすめ記事